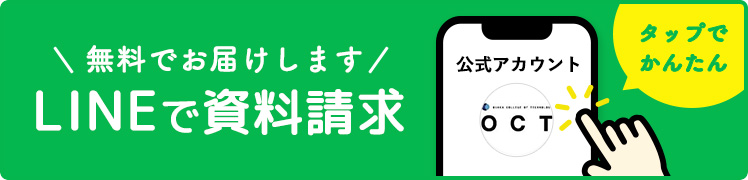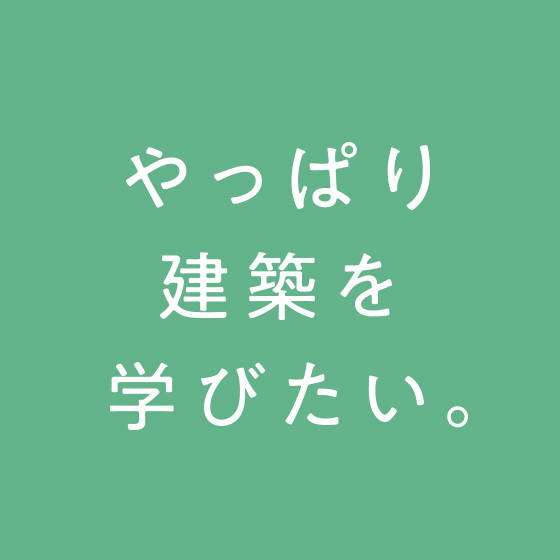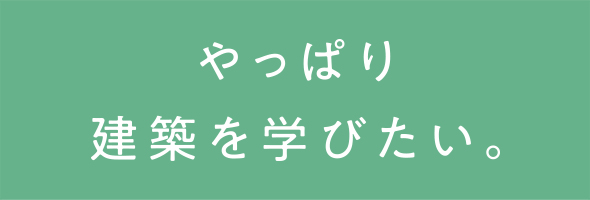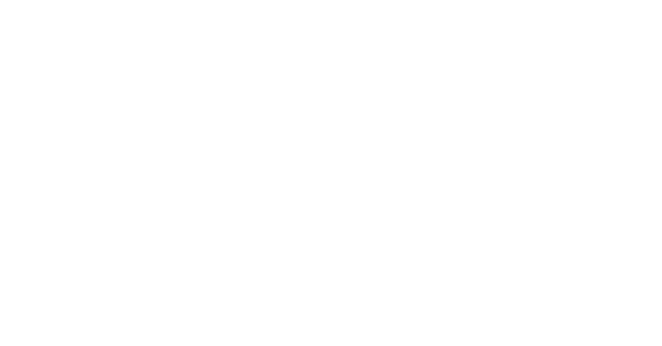(左):岸上純子先生 [担当:建築設計学科、インテリアデザイン学科]
(右):木村智子さん [所属:建築設計学科]
建築設計学科では、1年次に授業の一環としてチームで大阪市内のまちづくり提案に取り組みます。今年の舞台は大阪北区にある中津 。梅田に隣接し、うめきた開発地区と、昔ながらの地区が混在するまちです。中津の中であれば、何をテーマにするかは学生次第。2か月かけて自治会や住民の方にヒアリングを行い、中津を探索しながら学生自身で課題を発見し、最終は北区長や住民の方々の前でまちづくりの提案を行いました。担当教員・岸上先生とともに、提案を行うまでのプロセスを振り返りました。

▲「地蔵盆復活PROJECT」の企画提案を行ったチーム「PUT」
木村:実は、いままで中津のことはよく知らなかったんです。最初は何をして良いのかわからなくて、とにかく毎日まちを歩いていましたね。ところで、なぜ中津だったんですか?
岸上:中津を選んだのは、サーベイに適した面白い要素がまちの中にたくさんあることと、学生提案のような新しいアイデアを受け入れてくれるまちだから。この授業の目的は、建築の視点をもってまちを見ること。建築設計において敷地調査、サーベイは大事なことだからね。そういえば、今年は初めて座談会をやったんだよね。
木村:そうでしたね。12月に中津の自治会長や住民の方やまちづくりセンターの人が集まって、中津についていろんなお話を伺いました。まちの魅力や移り変わり、防犯の話、商店街のことなどなど……。

▲座談会の様子
岸上:地域の方から、具体的に「これを調べて欲しい」と要望も出ていたよね。客観的な目をもちながら、地域の人の意見を聞くのは難しかったと思う。でも、地域に入ってヒアリングをするのは、ただ観察するより視野が拡がるから意味のある事だよね。
木村:座談会の段階では、まだ地域に入りきれなかった印象です。でもおおまかにですが、中津に住む人たちの中津に対する認識はわかった気がしました。
岸上:最初の案は「オーニング」についてだったよね。しっかり調査はしていたけれど、着地点が見えなくて、先が不安だったわ……。
木村:そうなんです。結局、オーニングの案は行き詰まってしまったのですが、以前「お地蔵さんが多いね」と話していたことを思い出したんです。そこから情報を洗いなおしたところ、4丁目に地蔵盆がなくなってしまったことが判明しました。住人の「残したい」という希望に反してお地蔵さんが撤去されたことにも違和感があり、地蔵盆にテーマを変えたんです。

岸上:それが、最終発表の1,2週間前(笑)!
木村:それからは、建築的な視点でどうやって地蔵盆を考えていくかを話し合いました。いままで調査をやってきたオーニングとつなげて考えたり、歴史、伝統を大切にしつつどこまで崩すかを考えたり、ヒアリングをしたり……。あとは、とにかくピンポンしてお宅訪問しまくりました!(笑)
岸上:よく間に合わせたよねー。いままで積み上げてきたオーニングのスタディと、地蔵盆を合わせたのはよいアイデアだったと思う。地域の問題を取り入れ、いままでオーニングというモノに頼っていたのが、地蔵盆というコトと結びついて提案の強度が増した。
木村:最終的に「地蔵盆復活PROJECT」と題して、地域で地蔵盆を続けられる仕組みをつくりました。
今まで住民が地蔵盆を残したいと思いつつも、実践できなかったのは、管理者の所在と手法がわからないことが原因でした。運営の面では町会を中心に組織体系を構築して他の地域との連携をとりやすくしたり、地蔵盆の役割分担を行うことで運営側一人ひとりの負担を軽減する提案をしました。
手法としては、魅力的で簡単に設営可能な「地蔵盆テント」、子どもと簡易な「地蔵盆灯篭」をつくるWS、過去事例や使用できるアイデアを記載し情報の追加にも対応できる「地蔵盆 マニュアル カード」の作成を提案しました。

▲オーニングのスタディを応用した地蔵盆テント。誰でも簡単に設営できる。

▲子どもとつくる簡易地蔵盆灯篭は、お地蔵さん前の道をお祭りの空間に変える。

▲地蔵盆の事例をカードに。「どうやって開催すればいいのかわからない」という事態を防ぐ
岸上:最後の講評で区長さんが継承の仕方について触れていたけど、その辺りはどう考えていたの?
木村:実は、私以外のメンバーは地蔵盆を体験したことがないんです。だから「お供えはお菓子じゃないとダメ?」「それは必要あるの?」と、手軽にできるように地蔵盆のあり方を変えようという姿勢でした。でも、地蔵盆を経験しているわたしとしては、そのままのカタチで継承したい。

▲地蔵盆復活PROJECTは区長賞を獲得しました
木村:話し合った結果、「地蔵盆をみんなで一緒につくっていく」というアイデアにたどり着いたんです。メンバーが言っていた、「変わる」とは、地蔵盆の本質を変えることなく、それを取り巻く状態を今の現状に合わせて変えていくということだったんですね。それなら地域のひとが主体になれて、つながりにも発展しやすい。とても納得のいく考えでした。
岸上:この案はまちの人の前で発表する意義がすごくあったと思う。中津のお地蔵さんのほとんどは個人の持ち物となっているけれど、本来は地域で管理するものだったはず。こうやって問題が可視化され、危機感を伝えられたことで、地蔵盆を守るために動くきっかけになるかもしれないものね。
木村:そうですね。地蔵盆をテーマにした時「中津の地域の問題に寄り過ぎたかな」と思ったのですが、こういった事例は全国にたくさんあるんですよね。それがさらに高齢化、地域のコミュニティーという他の社会問題にもつながっていて、それは結構根深い問題だったりしますよね。
岸上:地域コミュニティーという意味では、小学校で行われているお祭りは根強く続いているみたい。これからは地蔵盆にもPTAなども巻き込んで、準備に関わってもらえるといいね。
木村:お祭りはやって終わりではなく、来年のお祭りとの間も人がいかに連続して繋がっていけるかだと感じました。お祭りをきっかけに繋がり続けていければいいですよね。
岸上:これだけ中津のこと考えてたら、愛着が湧いてくるよね。
木村:はい。今後も中津で、お地蔵さんを残す活動に関われればいいなと思っています。

photo: Natsumi Kinugasa
| すべてのプロジェクトを知りたい方はこちら 『プロジェクトで社会とつながる』一覧へ |